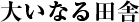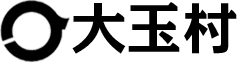【佳作】「知る」ことの大切さ 大玉中学校1年 渡辺希子
「知る」ことの大切さ
大玉中学校1年 渡辺希心
今回の広報からも、私の住む大玉村は「人権」という権利をとても大切にしている村だと思える。そのような村に育ち、私は、小学校四年生から人権作文に取り組んでいる。最初は「人権ってなんだろう?」ととても難しくて何を書いたらいいか、そうとう悩んだことを覚えている。人権というのがなんなのか少しずつわかってきても、それを文章にしてあらわすことは、とても難しかった。自分の体験や障がいのことを書く人も多くいたが、私は五体満足で、家族もみんな元気。自分自身のことを書くのは無理だなと思い、その度に人権に関係のある本をたくさん読んだ。今回は読んだ本の中で特に興味のあった「マイノリティ」について書こうと思う。
私は「マイノリティ」という言葉の意味がまったく分からなかった。本には「一つの集団に少ししかいない人たちのこと」と書いてある。となると、例えば、クラスには外国人が転校してきたとする。そうしたら、その人がマイノリティ。逆に私が外国人ばかりの学校に転校したら私がマイノリティとなるわけだ。もし私がマイノリティとなってしまった時は、不安で不安で仕方なくなると思う。「友達はできるかな?」「みんな話をしてくれるのかな?」「ひとりぼっちになってしまわないかな?」マイノリティとなってしまった日hとは皆、同じ悩みをもつと思う。
そして最近メジャーになりつつあるLGBT。これは「L=レズビアン(女性同性愛者)」「G=ゲイ(男性同性愛者)」「B=バイセクシャアル(両性愛者)」「T=トランスジェンダー(性別越境者)」の頭文字をとった言葉である。みんなが男らしさや女らしさを尊重すればするほど、LGBTの人たちはマイノリティになってしまうという。今や日本にも、十三人に一人ほどの割合でLGBTの人たちがいると言われている。LGBTの子どもたちは特に差別やいじめ被害の経験割合も高いという調査結果がでている。やはり子どもたちの中で見た目は男の子なのに、女の子らしいしぐさや行動を行ったら「えっ?」と違和感を覚える人もいると思う。それがもし、「人権」という権利を学んでいない子どもたちだったら、余計にそう思ってしまうはずだ。
もし私の近くにLGBTの人がいて、その事を話してくれたなら、私はその人のことを理解したいと思う。もちろんLGBTの人たちだけではない。マイノリティと呼ばれる人たち、みんなのことを理解してあげたい。
少数民族の人、職業による差別を受けている日人、この世界には本当に色々な人がいる。私のクラスにだって私と全く同じ人はひとりもいない。それぞれ、ひとりひとりが違うのだ。みんながひとりひとりを認め合うことで人権も守られていくのではないかと思う。
初めに述べたように、私たちの村の小学校は四年生から人権作文に取り組む。この取り組みがなければ、私は人権について考えることも、知ろうとすることもなかったと思う。人として早い時期に「人権」という権利を知れたことは本当によかった。まず人権という権利を知り、LGBTの問題を知り…、マイノリティの問題を知り…、高齢者虐待の問題を知っていく。すると、毎日のニュースの中で、「これも人権問題だな。」と思えることが多くある。
「知ること。」まずは人権という権利を知り、そして「あなた」を理解すること。知ることでさまざまな問題が解決する。知らないことでさまざまな偏見や差別がうまれるのではないかと思う。なるべく多くの人に知ってもらいたい。人権という権利を。LGBTを。マイノリティを。一人一人の考えが変わり、理解すれば世界も少しずつ良い方へと変わるのではないかと思う。
だから私は、いつでも目の前の「あなた」を理解し、知ろうとする私でいたい。
このページの情報に関するお問い合わせ先
大玉村TEL:0243-48-3131FAX:0243-48-3137
大玉村TEL:0243-48-3131FAX:0243-48-3137