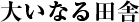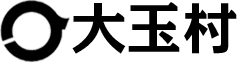【佳作】不自由な世界から見えること 玉井小学校6年 渡邉志帆
不自由な世界から見えること
玉井小学校6年 渡邉志帆
私は六年生になり、社会科の授業で人権について学びました。その時まで人権という言葉もよく知らなかったし、深く考えたりしたこともありませんでした。人権は、誰もが生まれながらにもっている権利で、それは自分にも関係あるということに気付くきっかけになりました。
でも、「人権って言われても、難しい」というのが正直な感想で、人権作文を書くことになり、何を書いたらよいのかとても悩みました。そこで、人権についてあらためて考えてみました。教科書を見たり、インターネットで調べたりして、人権は人々が不自由なく、平等に暮らせるために、守られている権利なんだということが分かりました。でも、本当にみんなが不自由なく、平等に暮らせているのだろうかと疑問に思いました。
私の母は病気をもっています。その病気は再発をくり返し、完全に治ることは難しい難病です。再発すると、身体がまひしてうまく動かせなくなったり、痛みで歩けなくなったりすることもあります。そういう時は、住み慣れた家の中や、ふだん行きなれた場所でも移動がつらそうです。階段を上がるのが難しい時もあり、とても大変そうです。身体が病気で何もない時には気にならなかったことが、身体が不自由になると急に不便になったり、困ったりするということを感じました。
でもこれは、障害がある人や、高齢で歩いたり移動したりするのが大変な人たちが、いつ
も感じていることなのではないかと思いました。バリアフリーやユニバーサルデザインのものは増えてきているけれど、身体の不自由な人が、困ることなく生活するためにはまだまだ足りないし、もっと考えることが必要な部分があると思います。
私は、母の具合が悪い時は、手を貸してあげたり、洗たく物を二階に持って行くなど、家の中のことを手伝ったりしています。他にも、自分のことはできるだけ自分でやるようにしています。でも、もし家族ではない他の人が困っていた時に、自分から声をかけられるかというと、かけられないかもしれません。
知らない人に声をかけるのは勇気がいるからです。それでも、自分では辛いと感じない移動を、大変そうにしている母を見ていると、他の困っている人を助けてあげられるようになりたいと思いました。
また、不自由だと感じるたくさんのことを、周りに意見として伝えて、みんなでどうした
らいいかと考えていける社会になっていったらいいなと思います。この社会には、子ども、大人、高齢者、健康な人、病気で苦しんでいる人などいろいろな人がいます。それぞれが相手のことを思って、助け合っていけると、困っている人が少なくなり、より良い世の中になるのではないかと思います。私も自分の立場からだけでなく、いろいろな人の立場になって考えられるように、努力していきたいと思います。
このページの情報に関するお問い合わせ先
大玉村TEL:0243-48-3131FAX:0243-48-3137
大玉村TEL:0243-48-3131FAX:0243-48-3137