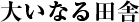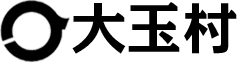【佳 作】「食品ロスを減らすには」 大玉中学校2年 馬場祐笑
佳作
「最近、牛乳残りすぎじゃない?」と、給食の時間に担任の先生が話題を振った。ふと見てみると牛乳入れのカゴにクラスの人数の半分以上の牛乳が残されていた。「自分は飲んでいるのに‥‥。」と心の中でつぶやきながら、どれくらいの量が残されているのかを計算してみると、私の家で消費されている牛乳の何日分もあった。酪農をやっている人にはこの現状をどう思っているのだろう。手塩にかけて育てた乳牛。その時間は長く、商いのためではない愛情があるだろうから、牛乳が廃棄されてしまうことなんて、願っていないだろう。その上、私たちは食に困っていない中で、世界には食べ物にもありつけない貧しい人達もいる。それなのに、「いらないから」という理由で捨ててしまうなんて、食べ物にも貧しい人達にも生産者にも、どこにもメリットはない。そして私は、「僕たちはどう生きるか」という本を読んで、「生産関係」という言葉を知って、より一層食品ロスの問題の大きさを知ったのだ。生産関係とは、人と人との間で何らかの関係を結んで行われているという意味である。本では、粉ミルクの例を用いて生産者と消費者の関係について書かれていた。あの給食の牛乳だって、状況は違ってもたくさんの人が携わっているに違いないし、様々な方法で関わっている人の努力もあるだろう。
このようなことから、私は「食品ロス」を減らすためにできる対策を2つ考えてみた。1つ目は、物を必要以上に買いすぎたり、長持ちしない物を買ってしまったりしないことなど、考えて食品を買うことだ。これは、食べられるはずの食品の廃棄を防ぐことにつながる。そうすれば、食品が捨てられる時のもったいなさや、この食品ロスの状況を緩和することに繋がるかもしれない。そして2つ目は、消費者が生産関係、そして生産者のことを考えることだ。例えば近年、生産者の顔が分かる野菜のパッケージなどがある。これらによって、消費者は安心して食品を買うことができる。また、生産者の顔を知っているから食品を思いやったり大切にしたりして食べることができる。この2つのことを忘れずに、私は食べ物に感謝したい。
600万トン。これらは何の量を表しているか。答えは「食べられるのにも関わらず廃棄される食品」の量。しかしその他にもう一つの答えがある。それは、生産者達の努力と消費者に食べてもらいたいという願いだ。この願いを叶えられるかは、私達の手にかかっているのだ。
「食品ロスを減らすには」
大玉中学校 2年 馬場 祐笑
600万トン。これは何の量を表しているか。答えは「食べられるのにも関わらず廃棄される食品」の量だ。これらは「食品ロス」という問題になっている。世界の食料不足に直面している国に対して支援できる援助量の2倍なのだからこれは驚く。私はこの問題で生産者はどう思うのだろうと考えたら、胸が痛くなった。「最近、牛乳残りすぎじゃない?」と、給食の時間に担任の先生が話題を振った。ふと見てみると牛乳入れのカゴにクラスの人数の半分以上の牛乳が残されていた。「自分は飲んでいるのに‥‥。」と心の中でつぶやきながら、どれくらいの量が残されているのかを計算してみると、私の家で消費されている牛乳の何日分もあった。酪農をやっている人にはこの現状をどう思っているのだろう。手塩にかけて育てた乳牛。その時間は長く、商いのためではない愛情があるだろうから、牛乳が廃棄されてしまうことなんて、願っていないだろう。その上、私たちは食に困っていない中で、世界には食べ物にもありつけない貧しい人達もいる。それなのに、「いらないから」という理由で捨ててしまうなんて、食べ物にも貧しい人達にも生産者にも、どこにもメリットはない。そして私は、「僕たちはどう生きるか」という本を読んで、「生産関係」という言葉を知って、より一層食品ロスの問題の大きさを知ったのだ。生産関係とは、人と人との間で何らかの関係を結んで行われているという意味である。本では、粉ミルクの例を用いて生産者と消費者の関係について書かれていた。あの給食の牛乳だって、状況は違ってもたくさんの人が携わっているに違いないし、様々な方法で関わっている人の努力もあるだろう。
このようなことから、私は「食品ロス」を減らすためにできる対策を2つ考えてみた。1つ目は、物を必要以上に買いすぎたり、長持ちしない物を買ってしまったりしないことなど、考えて食品を買うことだ。これは、食べられるはずの食品の廃棄を防ぐことにつながる。そうすれば、食品が捨てられる時のもったいなさや、この食品ロスの状況を緩和することに繋がるかもしれない。そして2つ目は、消費者が生産関係、そして生産者のことを考えることだ。例えば近年、生産者の顔が分かる野菜のパッケージなどがある。これらによって、消費者は安心して食品を買うことができる。また、生産者の顔を知っているから食品を思いやったり大切にしたりして食べることができる。この2つのことを忘れずに、私は食べ物に感謝したい。
600万トン。これらは何の量を表しているか。答えは「食べられるのにも関わらず廃棄される食品」の量。しかしその他にもう一つの答えがある。それは、生産者達の努力と消費者に食べてもらいたいという願いだ。この願いを叶えられるかは、私達の手にかかっているのだ。
このページの情報に関するお問い合わせ先
産業課農政係TEL:0243-24-8107FAX:0243-48-4448
産業課農政係TEL:0243-24-8107FAX:0243-48-4448