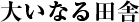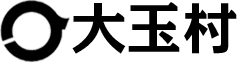【佳作】 「これからの農業」 大玉中学校2年 杉原ひなた
【佳 作】
まず、農業従事人口について調べることにした。
高度成長期に入る前の1940年頃の日本は1848万人の農業従事者が働いていた。それは全世帯の半分を占める数だったという。しかし、高度成長期に入った日本は減少が加速する形となり2000年には400万人を切った。現在の農業従事者は約150万人だ。
この課題を解決するために、スマート農業を取り入れるべきだと思った。
スマート農業とは、先端技術であるロボット技術やICTを用いて農作業を省力化、効率化することだ。
もし、スマート農業が取り入れられれば農業技術は大きく変化することになる。まず、先端技術の活用により少人数で管理がすむ。これは、課題を解決する鍵になるかもしれない。
また、スマホ一つで様々な管理ができたら「簡単そうだしやってみようかな。」と、声を上げる新規就農者が増加する可能性もある。
その可能性を高める言葉として3Kが挙げられる。3Kは厳しい、汚い、危険を指す言葉だ。このイメージが農業離れにつながり農業従事者が減少した要因の一つと考えられる。だからこそ、スマホ一つで行える手軽さが昔の農業のイメージを大きく変えることになり、新しいイメージを持たせる事ができるのではないか。と、考えた。
この課題に触れた当初は農業従事者の減少を食い止めることはできない。そう、思い込んでいた。
しかし、スマート農業を取り入れる考えを持ってから一変し、農業に関わる職業を今の時代に合った先端技術とかけあわせて増やすことで減少は食い止められると思った。きっと、高度成長期の日本から見た農業と今の農業のイメージは似ていて、3Kのようにマイナス面しか捉えない人が多いままなのだろう。私たちは農業へのイメージを変え、一から農業の課題に向き合う必要がある。
今、農業に危機が迫っている。あなたはどのように向き合っていくのか?
「これからの農業」
大玉中学校 2年 杉原 ひなた
農業に危機が迫っている。それは1950年頃の高度成長期に突入してから何一つ変わっていない。1950年の日本も若者が次々と都市へ就職するため農村から離れていったそうだ。そう、この課題は77年経った今でも大きな課題として残っている。日本の農業従事人口の減少と向き合うためにどのようにしたらよいだろうか。まず、農業従事人口について調べることにした。
高度成長期に入る前の1940年頃の日本は1848万人の農業従事者が働いていた。それは全世帯の半分を占める数だったという。しかし、高度成長期に入った日本は減少が加速する形となり2000年には400万人を切った。現在の農業従事者は約150万人だ。
この課題を解決するために、スマート農業を取り入れるべきだと思った。
スマート農業とは、先端技術であるロボット技術やICTを用いて農作業を省力化、効率化することだ。
もし、スマート農業が取り入れられれば農業技術は大きく変化することになる。まず、先端技術の活用により少人数で管理がすむ。これは、課題を解決する鍵になるかもしれない。
また、スマホ一つで様々な管理ができたら「簡単そうだしやってみようかな。」と、声を上げる新規就農者が増加する可能性もある。
その可能性を高める言葉として3Kが挙げられる。3Kは厳しい、汚い、危険を指す言葉だ。このイメージが農業離れにつながり農業従事者が減少した要因の一つと考えられる。だからこそ、スマホ一つで行える手軽さが昔の農業のイメージを大きく変えることになり、新しいイメージを持たせる事ができるのではないか。と、考えた。
この課題に触れた当初は農業従事者の減少を食い止めることはできない。そう、思い込んでいた。
しかし、スマート農業を取り入れる考えを持ってから一変し、農業に関わる職業を今の時代に合った先端技術とかけあわせて増やすことで減少は食い止められると思った。きっと、高度成長期の日本から見た農業と今の農業のイメージは似ていて、3Kのようにマイナス面しか捉えない人が多いままなのだろう。私たちは農業へのイメージを変え、一から農業の課題に向き合う必要がある。
今、農業に危機が迫っている。あなたはどのように向き合っていくのか?
このページの情報に関するお問い合わせ先
産業課農政係TEL:0243-24-8107FAX:0243-48-4448
産業課農政係TEL:0243-24-8107FAX:0243-48-4448