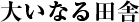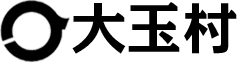【最優秀賞】 「これから農業を継ぐ身として」 大玉中学校2年 三瓶健太
【最優秀賞】
1つ目は、農業体験をすることだ。技術を学ぶのならば、体験をすることが一番だと思う。しかし、体験させてくださる農家さんがいるのか、体験した後どうするのかなど、課題もある。
2つ目は、様々な農業に関わる人から話を聞くことである。農業についてわからないこと、収入のことなど、農家さんや役場の方、直売所の方などに聞き、そこで得た知識をもとに仕事ができたら良いと思う。しかし、話を聞く機会をいつ作るのか、自分一人だけではできないことがある。そういった解決も、これからの農業に必要になってくると私は思う。
今、日本の食料自給率は低迷している。この現状をどう改善していくのか。環境への配慮、持続可能な農業、機械やドローンなどを取り入れて効率的に作業をするスマート農業など、これからの農業には考えなければならないことも多い。今回改めて思ったことは、農業はハードルが高い仕事かもしれないが、課題を抱え込まず、いろいろな人と協力し合えば、乗り越えていけるということだ。そしてその先には、明るい未来が待っていると思う。これから農業を継ぐ身として、今からでもできることをしていきたい。
「これから農業を継ぐ身として」
大玉中学校 2年 三瓶 健太
私の家では農業をしている。米作りだけではなく、畑では野菜を育てている。しかし、祖父母80代、父や母も会社との兼業で大変だと私は思った。そこで、長男である私が次の後継者となるのだが、まだ知識が浅く、中学生であるため、今すぐに継ぐのは難しいと自分自身思っている。しかし、いつまでも私が継がずにグズグズしていては、家族が「農業をやめる」という判断をしてしまうかもしれない。私は、それだけはなるべく避けたいと思っている。
では、一体どうすれば農業を続けることができるのか。まずは、農業の現状について調べてみた。令和3年度、主に農業を仕事としている人は約130万人。そのうち65歳以上は約90万人と、かなり多い。また、新しく農業に就く人は約5万4千人と、年々減少している。今の農業の現状は、高齢化が進み、後継者も少なくなっていき、衰退の一途をたどっているといえるだろう。だからこそ、私が継がなければいけないと思う。「農業をやってみたい」と思う人はいるだろうが、私と同じように「技術がない」「もうけが少ない」などの理由で二の足を踏んでいるかもしれない。そんな人たちにも農業に就くようにするために、方法を考えてみた。1つ目は、農業体験をすることだ。技術を学ぶのならば、体験をすることが一番だと思う。しかし、体験させてくださる農家さんがいるのか、体験した後どうするのかなど、課題もある。
2つ目は、様々な農業に関わる人から話を聞くことである。農業についてわからないこと、収入のことなど、農家さんや役場の方、直売所の方などに聞き、そこで得た知識をもとに仕事ができたら良いと思う。しかし、話を聞く機会をいつ作るのか、自分一人だけではできないことがある。そういった解決も、これからの農業に必要になってくると私は思う。
今、日本の食料自給率は低迷している。この現状をどう改善していくのか。環境への配慮、持続可能な農業、機械やドローンなどを取り入れて効率的に作業をするスマート農業など、これからの農業には考えなければならないことも多い。今回改めて思ったことは、農業はハードルが高い仕事かもしれないが、課題を抱え込まず、いろいろな人と協力し合えば、乗り越えていけるということだ。そしてその先には、明るい未来が待っていると思う。これから農業を継ぐ身として、今からでもできることをしていきたい。
このページの情報に関するお問い合わせ先
産業課農政係TEL:0243-24-8107FAX:0243-48-4448
産業課農政係TEL:0243-24-8107FAX:0243-48-4448