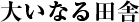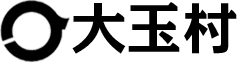【佳作】「食品ロスと消費者」大玉中学校2年 遠藤結衣
【佳 作】
皆さんは今日何を食べましたか。そしてそれを残さず食べましたか。私たちは普段何気なく食事をしていますが、残された食べ物はどうなってしまうのでしょうか。
「全部残すの?少しぐらい食べたら?」
ある日の給食の時間、食べ物の好き嫌いが多い私はいつも通り嫌いなものだけを食缶に戻しているところでした。そんなときある友達にそう問いかけられました。
「嫌いなんだから仕方ないでしょ。」
投げやりな態度で私は答え、その場を立ち去りました。今までは良くないと思いながらも「嫌いだから」という理由だけで残していた給食。改めて考えてみるとそれだけの理由で本当に残してもいいのか。そう考えさせられる問いかけでした。
このように、まだ食べられるのに食品が捨てられてしまうことを「食品ロス」といいます。FAO(国際連合食糧農業機関)の報告書によると、世界では食料生産の3分の1にあたる約13億トンの食料が廃棄されています。日本でも1年間に約612万トンもの食料が捨てられているそうです。これは国民1人あたりお茶碗1杯分のご飯を毎日捨てているという計算になります。環境省の調査によると、私が残していた給食も、全国では児童・生徒1人あたり年間約17.2キログラムの食品廃棄物が発生しているそうです。世界では8億人以上もの人が食べる物が足りず慢性的な栄養不足に苦しんでいます。その中で私たちは飽食で食品を捨てているのです。
「食品ロス」が問題視される理由は主に環境への負荷です。廃棄された食品は焼却処分や埋め立てなどにより処理されます。そのときに発生する二酸化炭素やメタンガスは地球温暖化などにも影響を及ぼします。他にも経済的な損失にもつながります。しかし、私は、もっと大事な理由があると考えました。それは、生産者の人の気持ちです。消費者である私たちのために、手間暇かけて作った食べ物を「嫌い」、「いらない」などの理由で捨てられることをどう思うでしょうか。天候に左右されながらも丁寧に育て、安全管理や衛生などに気を配りながら作ることは決して簡単なことではないはずです。どんな形であっても関わっている人たちの努力を軽い気持ちで捨てることはできないでしょう。
今では、「食品ロス」に対する取り組みとして、賞味期限切れの商品を安く販売する店や、廃棄された食品を飼料や肥料に再資源化するなどの取り組みがあります。
「全部残すの?少しくらい食べたら?」
この問いかけ以来、私は全て残すということをやめ、少しずつ食べる努力をしています。「食品ロス」を減らすのには、企業だけでなく消費者である私たち一人一人が意識を変えなければならないのです。
「食品ロスと消費者」
大玉中学校 2年 遠藤 結衣
皆さんは今日何を食べましたか。そしてそれを残さず食べましたか。私たちは普段何気なく食事をしていますが、残された食べ物はどうなってしまうのでしょうか。
「全部残すの?少しぐらい食べたら?」
ある日の給食の時間、食べ物の好き嫌いが多い私はいつも通り嫌いなものだけを食缶に戻しているところでした。そんなときある友達にそう問いかけられました。
「嫌いなんだから仕方ないでしょ。」
投げやりな態度で私は答え、その場を立ち去りました。今までは良くないと思いながらも「嫌いだから」という理由だけで残していた給食。改めて考えてみるとそれだけの理由で本当に残してもいいのか。そう考えさせられる問いかけでした。
このように、まだ食べられるのに食品が捨てられてしまうことを「食品ロス」といいます。FAO(国際連合食糧農業機関)の報告書によると、世界では食料生産の3分の1にあたる約13億トンの食料が廃棄されています。日本でも1年間に約612万トンもの食料が捨てられているそうです。これは国民1人あたりお茶碗1杯分のご飯を毎日捨てているという計算になります。環境省の調査によると、私が残していた給食も、全国では児童・生徒1人あたり年間約17.2キログラムの食品廃棄物が発生しているそうです。世界では8億人以上もの人が食べる物が足りず慢性的な栄養不足に苦しんでいます。その中で私たちは飽食で食品を捨てているのです。
「食品ロス」が問題視される理由は主に環境への負荷です。廃棄された食品は焼却処分や埋め立てなどにより処理されます。そのときに発生する二酸化炭素やメタンガスは地球温暖化などにも影響を及ぼします。他にも経済的な損失にもつながります。しかし、私は、もっと大事な理由があると考えました。それは、生産者の人の気持ちです。消費者である私たちのために、手間暇かけて作った食べ物を「嫌い」、「いらない」などの理由で捨てられることをどう思うでしょうか。天候に左右されながらも丁寧に育て、安全管理や衛生などに気を配りながら作ることは決して簡単なことではないはずです。どんな形であっても関わっている人たちの努力を軽い気持ちで捨てることはできないでしょう。
今では、「食品ロス」に対する取り組みとして、賞味期限切れの商品を安く販売する店や、廃棄された食品を飼料や肥料に再資源化するなどの取り組みがあります。
「全部残すの?少しくらい食べたら?」
この問いかけ以来、私は全て残すということをやめ、少しずつ食べる努力をしています。「食品ロス」を減らすのには、企業だけでなく消費者である私たち一人一人が意識を変えなければならないのです。
このページの情報に関するお問い合わせ先
産業課 農政係TEL:0243-24-8107FAX:0243-48-3137
産業課 農政係TEL:0243-24-8107FAX:0243-48-3137