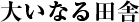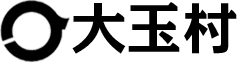【優秀賞】「虫の命も「いただきます」」大山小学校3年 菅野滉太
【優秀賞】
ぼくの家はお寺です。毎年、12月に「虫くよう」という行事があります。農作業でぎせいになった、田畑の虫たちをくようする行事です。
農家の人たちは、田畑をたがやす時、米や野さいを育てる時、しゅかくする時、気づかないうちにたくさんの虫をころしてしまいます。だから、今年1年間、知らず知らずにころしてしまった虫たちをくようするのだそうです。
農作業をする時、虫がいるとめいわくなことがたくさんあります。たとえば、土の中では根っこを切ってしまったり、新しく出てきためを食べてしまったりする虫がいるそうです。また、モンシロチョウもキャベツなどの葉にたまごをうみつけて、そこからよう虫が生まれて、葉を食べてしまいます。それから、わかい葉やくき、えだなどに、むれですんでしるをすって、野さいのせい長をじゃまする小さな虫もいます。
でも、虫がいないとこまることもあります。それは、実をつけるためのじゅふんです。ハチやチョウチョなどがみつをすいに花に止まることでじゅふんが行われるのです。
「こん虫の力をかりて滉太のすきなトマトが食べられるんだよ。」
と、お父さんが教えてくれました。ぼくは、虫を「めいわく」でじゃま者にしてはいけないと思いました。
ぼくの家では、米や野さいを買って食べているので、もちろん虫はついていません。ぼくは虫が苦手なので、虫がついていない方がいいです。虫がついていてもぼくが見ることは、ほとんどありません。
だけど、ぼくが食べている米や野さいにもしゅうかくされるまでに、たくさんの虫がぎせいになっていることを、今回あらためて知ることが出来ました。そこで、ぼくが出来る「虫くよう」は何だろうと、考えてみました。ぼくは、米や野さいを作ることは出来ないので、それを作ってくれる農家の人たちに感しゃすることと、お母さんが作ってくれる食事や、学校のきゅう食をのこさず食べることです。そして、その時、一つ一つの米や野さいにたくさんの虫の命がぎせいになっていることをわすれず、感しゃの気持ちをこめてあいさつします。
虫の命も「いただきます。」
「虫の命も「いただきます」」
大山小学校 3年 菅野 滉太
ぼくの家はお寺です。毎年、12月に「虫くよう」という行事があります。農作業でぎせいになった、田畑の虫たちをくようする行事です。
農家の人たちは、田畑をたがやす時、米や野さいを育てる時、しゅかくする時、気づかないうちにたくさんの虫をころしてしまいます。だから、今年1年間、知らず知らずにころしてしまった虫たちをくようするのだそうです。
農作業をする時、虫がいるとめいわくなことがたくさんあります。たとえば、土の中では根っこを切ってしまったり、新しく出てきためを食べてしまったりする虫がいるそうです。また、モンシロチョウもキャベツなどの葉にたまごをうみつけて、そこからよう虫が生まれて、葉を食べてしまいます。それから、わかい葉やくき、えだなどに、むれですんでしるをすって、野さいのせい長をじゃまする小さな虫もいます。
でも、虫がいないとこまることもあります。それは、実をつけるためのじゅふんです。ハチやチョウチョなどがみつをすいに花に止まることでじゅふんが行われるのです。
「こん虫の力をかりて滉太のすきなトマトが食べられるんだよ。」
と、お父さんが教えてくれました。ぼくは、虫を「めいわく」でじゃま者にしてはいけないと思いました。
ぼくの家では、米や野さいを買って食べているので、もちろん虫はついていません。ぼくは虫が苦手なので、虫がついていない方がいいです。虫がついていてもぼくが見ることは、ほとんどありません。
だけど、ぼくが食べている米や野さいにもしゅうかくされるまでに、たくさんの虫がぎせいになっていることを、今回あらためて知ることが出来ました。そこで、ぼくが出来る「虫くよう」は何だろうと、考えてみました。ぼくは、米や野さいを作ることは出来ないので、それを作ってくれる農家の人たちに感しゃすることと、お母さんが作ってくれる食事や、学校のきゅう食をのこさず食べることです。そして、その時、一つ一つの米や野さいにたくさんの虫の命がぎせいになっていることをわすれず、感しゃの気持ちをこめてあいさつします。
虫の命も「いただきます。」
このページの情報に関するお問い合わせ先
産業課 農政係TEL:0243-24-8107FAX:0243-48-3137
産業課 農政係TEL:0243-24-8107FAX:0243-48-3137