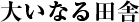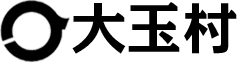食品ロス
健康寿命の延伸につながる食育・食の循環や環境を意識した食育
栄養成分表示を使って肥満とやせを防ぐ
〔肥満とやせについて〕
肥満は、高血圧、糖尿病、心臓病など様々な生活習慣病の原因になります。
やせや低栄養は、虚弱の原因となり、特に高齢期では要介護状態や死亡のリスクを高めます。
健康長寿社会の実現に向け、生活習慣病や虚弱を予防するために、肥満・やせを予防・改善し、適正体重を維持することが大切です。
肥満は、高血圧、糖尿病、心臓病など様々な生活習慣病の原因になります。
やせや低栄養は、虚弱の原因となり、特に高齢期では要介護状態や死亡のリスクを高めます。
健康長寿社会の実現に向け、生活習慣病や虚弱を予防するために、肥満・やせを予防・改善し、適正体重を維持することが大切です。
実践のポイント(体重の計測と食品の選び方で、肥満とやせを防ぐ)
⒈やせている?太ってい? 自分の適正体重を知ろう
目標とするBMIの範囲(18歳以上)
目標とするBMIの範囲(18歳以上)
| 年齢(歳) | 目標とするBMI |
| 18~49 | 18.5~24.9 |
| 50~64 | 20.0~24.9 |
| 65~74 | 21.5~24.9 |
| 75歳以上 | 21.5~24.9 |
出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」2019年
BMIを計算してみましょう
体重( )kg÷身長( )m÷身長( )m=自分のBMI
※肥満、やせは、BMI(BodyMassIndex)による判定
体重( )kg÷身長( )m÷身長( )m=自分のBMI
※肥満、やせは、BMI(BodyMassIndex)による判定
2.栄養に関する表示を見比べよう
健康づくりや生活習慣病の予防のためには、カロリ-(エネルギ-)や食塩の調整が有効です。食品や外食のメニューなどに見られる栄養成分の記載や減塩、低カロリーといった表示は、選ぶ際の目安になります。
◎食品のもつエネルギーを確認して選ぶ
◎炭水化物を多く含む食品とたんぱく質を多く含む食品を組み合わせて選ぶ
健康づくりや生活習慣病の予防のためには、カロリ-(エネルギ-)や食塩の調整が有効です。食品や外食のメニューなどに見られる栄養成分の記載や減塩、低カロリーといった表示は、選ぶ際の目安になります。
◎食品のもつエネルギーを確認して選ぶ
◎炭水化物を多く含む食品とたんぱく質を多く含む食品を組み合わせて選ぶ
| 栄養成分表示 1食(○g)当たり |
| エネルギー ○Kcal ここをチェック |
| たんぱく質 ○g ここをチェック |
| 脂質 ○g |
| 炭水化物 〇g ここをチェック |
| 食塩相当量 ○g |
もったいないを意識して食品ロスを減らす
日本における食品ロスの量は年間約643万トンを超え、食料を海外からの輸入に大きく依存しながら、大量の食料が食べられないまま廃棄されています。「もったいない」という意識を持ち、適量を選び、食べきることなど一人ひとりができることから始めて、食品ロス削減に取り組むことが大切です。
(国民1人当たり食品ロス量)
1日約139g 茶碗約1杯のご飯の量に相当
資料:総務省人口推計(平成28年度)平成28年度食料需給表(概算値)
実践のポイント 買い方を変えて、食品ロスを減らす
1買い物に行く前には家にある食材をチェックしてから行く
・スマホで冷蔵庫や食品庫の写真を撮って買いに行くのもおすすめ
2家にある食材を優先的に使うことを考えて
・家にある食材を使った献立を考えてみましょう
・残っている食材から使いましょう
・作り過ぎてしまい残った料理は、リメイクレシピ(残った料理をアレンジして、別の料
理に変身させるレシピのこと)などで工夫しましょう
リメイクレシピについては、消費者庁ホームページ[消費者のキッチン]で紹介されて
います。
3使い切る分だけ買い物をしよう
・カット野菜は割高感がありますが、少量だけ必要な場合には利用してみてはいかがでし
ょう。切らずにそのまま使えるのも便利。
4人や社会、環境のことも考えて買いものをしよう
・今日使うものなら、賞味期限の近い物から買いましょう
5食材を適切に保存する
・食品に記載された保存方法に従って保存する
・野菜は、冷凍・茹でるなど下処理して、ストックする
・スマホで冷蔵庫や食品庫の写真を撮って買いに行くのもおすすめ
2家にある食材を優先的に使うことを考えて
・家にある食材を使った献立を考えてみましょう
・残っている食材から使いましょう
・作り過ぎてしまい残った料理は、リメイクレシピ(残った料理をアレンジして、別の料
理に変身させるレシピのこと)などで工夫しましょう
リメイクレシピについては、消費者庁ホームページ[消費者のキッチン]で紹介されて
います。
3使い切る分だけ買い物をしよう
・カット野菜は割高感がありますが、少量だけ必要な場合には利用してみてはいかがでし
ょう。切らずにそのまま使えるのも便利。
4人や社会、環境のことも考えて買いものをしよう
・今日使うものなら、賞味期限の近い物から買いましょう
5食材を適切に保存する
・食品に記載された保存方法に従って保存する
・野菜は、冷凍・茹でるなど下処理して、ストックする
実践のポイント 適量とともに、食品の安全も考えよう
1健康維持の基本、「栄養栄養バランスのとれた食事、適度な運動、十分な休養」
2色々な産地の食材で、栄養バランスを考えた献立をつくりましょう。
「やせる」=「消費エネルギー>摂取エネルギ-」ですが、食事の減らし過ぎは必要な筋
肉量の減少を招きます。適度な運動と食事のコントロールの両方が大切です。
3過労や睡眠不足は万病の元
・食べきる分だけ作る、小分けにしてすばやく冷蔵、食べるときに十分に全体を再加熱し
ましょう。
・塩漬けしたり乾燥させても増殖する細菌
・カビがありますから、早めに食べきりましょう。
・冷蔵庫を過信しない
冷蔵庫に食品を詰めすぎると更に温度は下がりにくいので注意が必要です。食中毒防止
の観点からも、買い物ときから適量を意識しましょう。
・食品の期限表示(賞味期限・消費期限)について、正しく知る
◎賞味期限:おいしく食べることができる期間
◎消費期限:過ぎたら食べない方がよい期限
消費できる量を購入し、期限内に食べきりましょう。
※上記の説明は、未開封の状態で、食品に記載されているとおりに保存した場合の期限で
す。一度開封した食品は、期限に関わらず早めに食べきりましょう。
・冷蔵庫をチェックする日を決めて、無駄に捨てられてしまう食材を減らしましょう。
引用-参考文献:消費者庁ウェブサイト・家庭での食品ロスを減らそう[消費者庁]めざせ!食品ロス・ゼロ、[食品ロス削減]食べ物のムダをなくそうプロジェクト健康と環境に配慮した適 量のすすめ
2色々な産地の食材で、栄養バランスを考えた献立をつくりましょう。
「やせる」=「消費エネルギー>摂取エネルギ-」ですが、食事の減らし過ぎは必要な筋
肉量の減少を招きます。適度な運動と食事のコントロールの両方が大切です。
3過労や睡眠不足は万病の元
・食べきる分だけ作る、小分けにしてすばやく冷蔵、食べるときに十分に全体を再加熱し
ましょう。
・塩漬けしたり乾燥させても増殖する細菌
・カビがありますから、早めに食べきりましょう。
・冷蔵庫を過信しない
冷蔵庫に食品を詰めすぎると更に温度は下がりにくいので注意が必要です。食中毒防止
の観点からも、買い物ときから適量を意識しましょう。
・食品の期限表示(賞味期限・消費期限)について、正しく知る
◎賞味期限:おいしく食べることができる期間
◎消費期限:過ぎたら食べない方がよい期限
消費できる量を購入し、期限内に食べきりましょう。
※上記の説明は、未開封の状態で、食品に記載されているとおりに保存した場合の期限で
す。一度開封した食品は、期限に関わらず早めに食べきりましょう。
・冷蔵庫をチェックする日を決めて、無駄に捨てられてしまう食材を減らしましょう。
引用-参考文献:消費者庁ウェブサイト・家庭での食品ロスを減らそう[消費者庁]めざせ!食品ロス・ゼロ、[食品ロス削減]食べ物のムダをなくそうプロジェクト健康と環境に配慮した適 量のすすめ
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健課健康長寿推進係TEL:0243-48-3130FAX:0243-68-2789
保健課健康長寿推進係TEL:0243-48-3130FAX:0243-68-2789