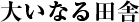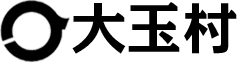十楽院のカヤ(緑の文化財)、馬頭観音
「十楽院」について
昔、毎夜地中より不思議な光が発し、里人が鋤(すき)で掘ってみると中から美しい顔立ちの観音様が出てきた。重楽院と称する修験者が、観音堂を作りこれを鎮座したことから重(十)楽院の名がついたと言う。掘りだした時の鋤の傷跡が今も残る。村指定文化財。
「ある農夫が馬を連れてこの辺り(現在の玉井字的場付近)まで歩いてきたところ、急に馬がひざまずいて動かなくなった。不思議に思った農夫が畑を掘り起こしてみたら、この観音様が出てきた。それで、ここの観音様は馬頭観音様になった。」という伝説もある。
この像は馬頭観音といわれているが、左手下方に蓮茎の一部が残っている。この像の印相は、左手に蓮華、右手は第一・二指頭を捻じるもので、聖観音のものである。しかし、宝冠には宝瓶をつけており、勢至菩薩ともみられる。(『企画展 中通りの仏像』より)
「ある農夫が馬を連れてこの辺り(現在の玉井字的場付近)まで歩いてきたところ、急に馬がひざまずいて動かなくなった。不思議に思った農夫が畑を掘り起こしてみたら、この観音様が出てきた。それで、ここの観音様は馬頭観音様になった。」という伝説もある。
この像は馬頭観音といわれているが、左手下方に蓮茎の一部が残っている。この像の印相は、左手に蓮華、右手は第一・二指頭を捻じるもので、聖観音のものである。しかし、宝冠には宝瓶をつけており、勢至菩薩ともみられる。(『企画展 中通りの仏像』より)
十楽院のカヤ(緑の文化財)
本院のある馬喰内一帯は、弥生式土師器時代の遺跡であり、隣接地大畑とその北200メートルの所にも古代の寺跡があり、布目瓦など出土するのをみても、この寺院も創立は非常に古いものと思われる。
詳細は、指定文化財の紹介ページをご覧ください。
馬頭観音
昔、毎夜地中より不思議な光が発し、里人が鋤で掘って見ると中から美しい顔立ちの観音様が出てきた。
これを十楽院と称する修験者が観音堂を作り鎮座したことから名が付いたという。(掘り出した時の鋤の傷跡が今も残る。)
これを十楽院と称する修験者が観音堂を作り鎮座したことから名が付いたという。(掘り出した時の鋤の傷跡が今も残る。)

詳細は、指定文化財の紹介ページをご覧ください。
所在地
福島県安達郡大玉村玉井字馬喰内
このページの情報に関するお問い合わせ先
産業課商工観光係TEL:0243-24-8096FAX:0243-48-4448
産業課商工観光係TEL:0243-24-8096FAX:0243-48-4448