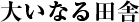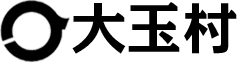福島県民会規則
大玉村指定有形文化財(歴史資料)
福島県民会規則
所 有 者 大玉村
所有者の住所 福島県安達郡大玉村玉井字星内70番地
所在の場所 福島県安達郡大玉村玉井字西庵183番地(あだたらふるさとホール内)
数 量 1冊
法 量 17.8cm×12.0cm
時 代 明治時代(明治11年1月公布)
民会は、町・村会-区会-県会からなる。当初は、廃藩置県等明治維新後の近代化政策による混乱を収めるために上からの機関として設けられたものであるが、明治7年(1874)の民撰議院設立建白による自由民権運動の全国的展開を契機として地域の民意を反映できる機関となっていった。特に本県においては、河野広中が区長となった常葉町や石川町に開設した民会がよく知られている。
本県は明治9年に磐前(いわさき)県・福島県・若松県の3県が合併し現在の福島県の基となる福島県が成立したが、これによりそれぞれの県で進展してきた民権運動が合同し、より進歩的な運動へと発展していった。
こうした中で「麁抹(そまつ)過激の二弊を免れ、協和忠愛真正の実益を求め」「公益を謀り私論を禁じ、遂に公撰議会の実旨を貫徹」するため、区戸長会の審議、修正を経たうえで、福島県が明治10年12月に定め、翌11年1月に福島県民会規則を公布した。
福島県民会規則は、「町村会規則」「区会規則」「県会規則」「県会内規則」と旅費等について定めた付録から成る。なお、『福島県民会規則略解 全』(明治11年5月刊、野口勝一解、川又定蔵出版)が漢字平かな体、総ルビであるのに対して、現資料は漢字片かな体、ルビなし、である。
民意が、町村会→区会→県会と有機的・段階的に達せられる仕組みになっていること、各規則の第一章は議員選挙について書かれ、財産制限はあるが、選挙権を満20歳以上の男子に、被選挙権を満25歳以上の男子に賦与する公選制であることなど、この時期の政治の仕組みとしては画期的なものであった。
本資料は、本村大山字象目田の角田(かくた)剛氏より村へ寄贈されたものであるが、明治38年に角田家高祖父の弟彌助と、新殿村大字杉沢(現二本松市杉沢)の菅野(かんの)新吉の娘キヨの結婚に際し、携行してきたものと思われる。この結婚の際に証人として立ち会ったのが菅野丈吉で、丈吉は父喜三郎とともに自由民権運動で活躍した人物であるが、民権運動が下火になってからも、地租増徴反対運動で活躍し、また「杉沢夜学会」の運営の中心的役割を果たした人物である。キヨと丈吉、キヨの父新吉の民権運動との関わりなどは不明であり、今後の資料の発掘等を待たなければならないが、安達郡内の自由民権運動の高まりを示す貴重な歴史資料であり、現存する「福島県民会規則」の現物資料は数点であること、洋紙活版印刷のため安定した状況での保存が必要であることなどを考えると、大玉村指定文化財として保護を図っていくことが適切と思われる。
福島県民会規則
所 有 者 大玉村
所有者の住所 福島県安達郡大玉村玉井字星内70番地
所在の場所 福島県安達郡大玉村玉井字西庵183番地(あだたらふるさとホール内)
数 量 1冊
法 量 17.8cm×12.0cm
時 代 明治時代(明治11年1月公布)
民会は、町・村会-区会-県会からなる。当初は、廃藩置県等明治維新後の近代化政策による混乱を収めるために上からの機関として設けられたものであるが、明治7年(1874)の民撰議院設立建白による自由民権運動の全国的展開を契機として地域の民意を反映できる機関となっていった。特に本県においては、河野広中が区長となった常葉町や石川町に開設した民会がよく知られている。
本県は明治9年に磐前(いわさき)県・福島県・若松県の3県が合併し現在の福島県の基となる福島県が成立したが、これによりそれぞれの県で進展してきた民権運動が合同し、より進歩的な運動へと発展していった。
こうした中で「麁抹(そまつ)過激の二弊を免れ、協和忠愛真正の実益を求め」「公益を謀り私論を禁じ、遂に公撰議会の実旨を貫徹」するため、区戸長会の審議、修正を経たうえで、福島県が明治10年12月に定め、翌11年1月に福島県民会規則を公布した。
福島県民会規則は、「町村会規則」「区会規則」「県会規則」「県会内規則」と旅費等について定めた付録から成る。なお、『福島県民会規則略解 全』(明治11年5月刊、野口勝一解、川又定蔵出版)が漢字平かな体、総ルビであるのに対して、現資料は漢字片かな体、ルビなし、である。
民意が、町村会→区会→県会と有機的・段階的に達せられる仕組みになっていること、各規則の第一章は議員選挙について書かれ、財産制限はあるが、選挙権を満20歳以上の男子に、被選挙権を満25歳以上の男子に賦与する公選制であることなど、この時期の政治の仕組みとしては画期的なものであった。
本資料は、本村大山字象目田の角田(かくた)剛氏より村へ寄贈されたものであるが、明治38年に角田家高祖父の弟彌助と、新殿村大字杉沢(現二本松市杉沢)の菅野(かんの)新吉の娘キヨの結婚に際し、携行してきたものと思われる。この結婚の際に証人として立ち会ったのが菅野丈吉で、丈吉は父喜三郎とともに自由民権運動で活躍した人物であるが、民権運動が下火になってからも、地租増徴反対運動で活躍し、また「杉沢夜学会」の運営の中心的役割を果たした人物である。キヨと丈吉、キヨの父新吉の民権運動との関わりなどは不明であり、今後の資料の発掘等を待たなければならないが、安達郡内の自由民権運動の高まりを示す貴重な歴史資料であり、現存する「福島県民会規則」の現物資料は数点であること、洋紙活版印刷のため安定した状況での保存が必要であることなどを考えると、大玉村指定文化財として保護を図っていくことが適切と思われる。
- 抜粋写真(PDF形式:598KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
教育委員会生涯学習課TEL:0243-48-3139FAX:0243-48-3493
教育委員会生涯学習課TEL:0243-48-3139FAX:0243-48-3493