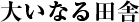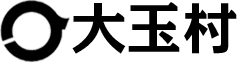【佳作】画面の向こうの人権 大玉中学校2年 伊藤琉生
画面の向こうの人権
大玉中学校2年 伊藤 琉生
現代社会で欠かせないもの。いろいろなものが思いうかぶ。インターネットもその中の一つだ。小さい子供から高齢者の方々まで幅広い年齢層に普及している。分からないことがあればすぐ調べられる。そして、様々な人種、国や異なる言語の人とつながれる。おそらく使い道はほとんどの人が知っているだろう。そして、その反面、人を傷つける凶器となる事も当然多くの人が知っているはずだ。インターネットの被害はジワジワ表面化している。これだけ深刻な問題となっているのになぜ無くならないのか。インターネットの恐ろしさ。それは、その影響がそれぞれの受け取り方次第という事である。例えばナイフで木の板を切ったら切り傷がつく。それはどんな使い方をしても傷しかつかない。銃を使ったら、穴があく。今の二つを人に使ったら怪我をしてしまうし、命を落とすこともあるだろう。使ったことのない人も、使った事のある人も、その危険性を知っているから普通は使おうとしない。しかし、言葉は分からない。
「バカ。」この一言をネットに打ちこむ。それを見て怒る人もいるが悲しむ人もいる。直接言ったとき、言った人の表情で言葉の重みは変わる。笑っていたら軽い意味になり、真剣な表情をしていれば、何か理由のある重い言葉となる。だが画面に映る「バカ」は表情は分からない。感じ方によって刃はするどくなり、強力な銃弾となる。この言葉よりも嫌な言葉がネット上を飛び交う。その言葉を受けた人の心の傷は、計りしれない。
誹謗中傷をする人の割合で多いのが、主婦や大学生という話を聞いたことがある。どちらもストレスは溜まりやすい立場だ。その中の一部の人が、芸能人や自分とは違う価値観の人をターゲットに、暴言でストレスの吐きだめに使うことが多いらしい。はたしてその人達は、本人を前に同じことが言えるのだろうか。言えないはずだ。直に意見を伝えることと、インターネットに意見を書きこむことは大きく異なる。誹謗中傷を受けた人が、うつ病になったり、自ら命を絶ったとき、身内の人や、関係者はとても悲しむ。だが、暴言を書きこんだ人は、心から悲しむことはできないはずだ。一時の感情に任せた自分の浅はかな言葉の結果に、罪悪感を感じる人もいるかもしれない。しかし、自分が責められることへの恐怖に、証拠を消す人もいる。彼らは書きこむとき、画面の向こうの人権を考えていないと僕は思う。「見えないだけ」で、たしかに人はそこにいて、その人にも人権はある。僕に他の人の人権を奪う権利はない。もちろん他の人にもない。人権を守る上で一番重要なのは違いを認める心だ。これはどんな事にも通じる。簡単そうだが、意外と難しい。
僕は音楽が好きだ。僕が好きなアーティストの動画を見たとき、視聴者のコメント欄にこのアーティストの音楽を否定するコメントが書きこまれていた。このアーティストのファンが多いこの欄にそのような事を書く人に僕は少し怒りを感じたが、そのコメントに対する返信に驚いた。たった一人に対し、百何十人という人が「バカ」や「消えて」など見ていられないような言葉を書きこみ、死ねの隠語まで使われていた。元々の原因を書きこんでしまった本人は、「傷つけるつもりはなかった。」と謝罪していたが・・・。それでも止まらない暴言の雨。一人の違う考えに、多勢の違いを認められない心がこんなにも集中して傷つけることにとても残念な気持ちになった。友人の好きなアーティストをあまり好きではないと言ってしまったとき、友人はバカや消えろなどの嫌な言葉は言わなかった。批判的なコメントをした人も、言い方が悪かっただけなのだ。それに対しての反論も言い方を考えるべきだ。
「みんな違ってみんないい」この世界は自分と同じ意見の人よりも、違う意見の人のほうが多い。それぞれの価値観がある。違いを認め合う心さえあれば、ネット上の深い人権問題もすぐに解決すると思う。
文明の発展によって、様々なことができるようになった。インターネットでは多くの情報を得られる。だが、そこで埋もれて見えなくなるものが人権ではないだろうか。画面越しにやり取りしている相手はロボットではなく、人なのだ。これからの未来、さらにインターネットを使う機会は増えていく。その時僕は、画面の向こうにある人権を意識することを心がけていきたい。そして、いつの日かインターネットで涙を流す人がいなくなることを願う。