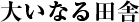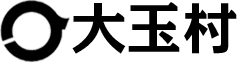【特選】インターネットと人権 一般部門 斎藤徹
インターネットと人権
一般部門 斎藤 徹
「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、尊厳と権利とについて平等である」第一条で始まる世界人権宣言が採択されて今年で七十周年を迎えます。時代の変化と共に、人権問題は複雑化し、中でもインターネットの急速な普及によって青少年が深刻な人権被害にさらされるケースが増えてきました。ご存じのように、つい最近、SNSによる誹謗中傷により某女子プロレスラーが、二十二歳の若さで自ら命を絶つという悲しい出来事が起きております。罪もない人間が、見知らぬ人たちから誹謗中傷を受け、それらの行為が、どれだけ本人を苦しめ、悩ませ、悔しさに耐えてきたか、想像しがたい。まさに「言葉は時には恐ろしい凶器と化する」と言うが、その言葉の凶器によって、彼女は「死」を選ばされたのです。このように人権を無視した行為が、自分の身内に起きたならば、果たして冷静な気持ちで対応できるであろうか?否、私は、冷静さを失い絶対に許すことは出来ないと思う。フェイスブックのように実名を公開し、近況や画像を投稿して、他の利用者との交流の中で「いいね」を連発し合いながら楽しむのは、誠にほほえましいものです。しかし、その匿名性、情報発信の容易さから個人の名誉やプライバシーを侵害したり差別を助長する表現を掲載したりするなど人権に関わる様々な問題が生じています。情報は広く大勢の人々に伝わってしまいます。一度公開された情報は完全に消去することは、難しいという。情報を書き込まれた人は、周囲の人々から誤解され、日常生活に大きな支障を、きたしかねません。さらに精神的に深く傷つき、追い詰められ、体の不調を訴えたり、職場や学校に行けなくなり、自殺へと繋がりかねません。コミュニケーションの手段としての生活を飛躍的に便利なものにしたのも間違いありません。近年では、携帯電話、特にスマートフォンの普及に伴い、子供たちにとって身近なものになった。その一方で保護者や教員の知らない非公式サイトでの「いじめ」が大きな問題になっている。このような卑劣な誹謗中傷を、なくすために発信者の特定を容易にするために、一日も早く制度改正を、スピード感をもって取り組んで頂きたい。人権に関しては、幼児期から家庭教育が、いかに大切か、また学校教育、社会教育の中で、「他人を思いやる」「人を人として尊重する」という気持ちを育んで行くことが大切なのではないでしょうか。